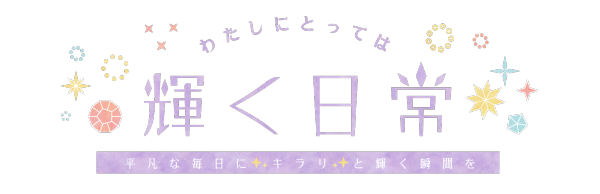[chat face="smile-1.png" name="みゆも" align="left" border="none" bg="gray"]こんにちは。みゆも(@miyumo_3boysmom)です![/st-kaiwa1]
子どもを育てていて
- う~ん。どうも育てにくい子だなぁ。
- なんか、育児書通りに成長していかないなぁ。
- ネットでお悩みを検索したら、大体、“○○ 発達障害”がセットで出てくる!
ということはありませんか?
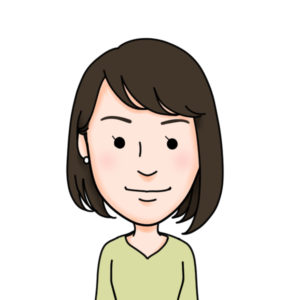
我が家の長男の場合、気になりだしたのは1歳半頃から。
やたら、数字や文字にハマりだしたことがきっかけでした。
「1歳半で数字数えられたり、文字読めたりするんだっけ!?」
と気になり、軽い気持ちでネット検索したところ、セットで出てきたのは“発達障害”や“自閉症”の文字。
検索結果にもズラリとそういった記事が並んでいました。
その後、言葉が遅いことやその他のこだわりが強いことなど、検索するたびにセットで出てくる“発達障害”の文字・・・
その他にも諸々気になるところがあり、2歳半頃に市の発達相談へ行き、その後、発達支援教室に週1回、半年ほど幼稚園入園までの昨年3月まで通っていました。
ハッキリとした診断名はついていないものの、その頃に受けた小児科医の方との面談の時に、相談内容や面談時の長男の様子から“自閉症傾向あり”というようなことを言われています。
しかし、2~3歳の頃はそういった発達障害の特性が多々見られていた状態でしたが、その後、幼稚園(こども園)に入園して、家族以外の大人たちや同年代のお友達と関わることが増え、最近では、だいぶその特性が目立たなくなってきました。
昨年の今頃は、その発達支援教室を卒業し、幼稚園(こども園)への入園を迎え、
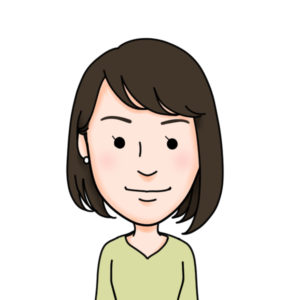
と不安になっていた頃です。
ただ、今考えると、幼稚園入園前に発達相談を受け、支援教室へ通ったことは、
本当によかった。入園前に早めに動いてよかった。
と思っています。
もし、「なんか、うちの子、周りの子と違う気がする・・・」と気になる点があって、発達相談へ行くことを迷っている方がいたら・・・
我が家の体験談がひとつのきっかけになればいいな。ということで、
発達相談はどんなことをするのか?
というのをお話できればと思います。
子どもの発達について相談するにはどうすればいいの?
まずは、自治体の発達相談窓口へ電話などで連絡をします。
「○○市 発達相談」
などで検索すれば、窓口になる課が出てくると思うので、そちらへ連絡を入れてみましょう。
あとは、1歳半健診などで保健師さんに相談してみると、そのまま発達支援の方につないでくれる場合も多いかと思います。
実際に相談を受けられるのは数ヶ月待ちだったりする!
ここ最近、発達障害関連のテレビ番組や本なども多く出されていて、芸能人で『発達障害』を告白する方もいたりして、認知が広がっている気がします。
また、ネットが普及したことで簡単に疑問に思ったことをネット検索できるので、そういったネット情報を見て不安になり、相談に行かれる親御さんも多いかと思います。
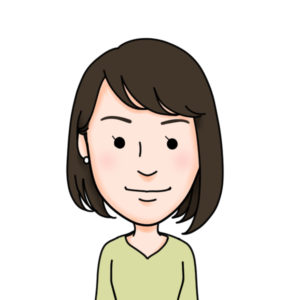
相談数も増えているようで、自治体に連絡をしたとしても2~3ヶ月待ちや半年待ちというのもよく聞く話です。
我が家の場合、6月に児童発達支援課に電話連絡を入れ、1週間後に相談員さんとのちょっとした面談がありました。
その時に、「では、一度小児科医の先生が来る発達相談を受けてみますか?」と言われました。
月に1回しかないもので、翌月の枠は埋まっていたので、2ヶ月後の8月下旬に発達相談受けることになりました。
実際に、私の友人でも何人か発達相談を受けた親子がいるのですが、大体2~3ヶ月待ちが多かったです。
結局、自治体の支援課に連絡を入れても、実際に発達相談を受けられるのは数ヶ月待ちになることが多いので、ネットの情報でもやもやしている期間があるのなら、まずは早めに自治体の相談窓口に相談してみるといいと思います。
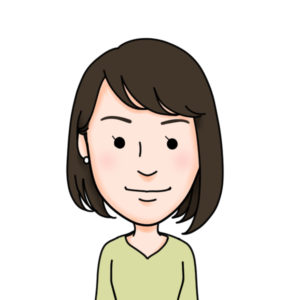
発達相談を受けるまでの私の気持ち
ここ数年で、『児童発達支援課』のような名称で、ちょっと発語が遅かったり、その他の発達が遅めの子も、就園・就学までに支援を受けられるような課が設けられるようになりました。
発達障害の場合、普通に生活できる軽度なものから、知的障害を伴い自分一人で生活するのが少し難しいような程度まで様々で、特性の種類も様々です。
『障害児支援』というと、
「うーん・・・ちょっと育てにくいだけで“障害”とは違うような・・・。」
と相談も躊躇してしまいますが、『児童発達支援』という名称であれば、相談までのハードルが低く感じますよね。
私も、なんだか長男の育てにくさを感じつつも、普通に目は合うし、言葉も全く出ていないというわけではなかったので、相談へ行くことをかなり迷いました。
発達相談へ行く=診断を受ける
というのと混同していたので、
- 相談へ行って、『発達障害』が確定してしまったら、この子は“障害児”になってしまうんだろうか。
- 少し発達が遅いだけで、普通に生活は出来るのに、障害者のレッテルを貼ることにはならないだろうか。
- この程度なら、相談へ行かなければ障害者にはならないだろうか。
- もし、発達障害で希望している幼稚園へ入園できなくなったらどうしよう。
というようなことを思っていたと思います。
ただ、発達支援課へ相談へ行った時に、相談員さんがとても丁寧に、慎重に、言葉を選んで“発達障害”というものについてお話してくれ、2~3歳は発達の個人差が大きい時期でもあるので、
発達相談へ行く=即診断ではない
ということが分かり、安心しました。
これを不安に思う親御さんも多いと思いますが、わが家の住んでいる自治体では、発達障害の診断についてはかなり慎重にやっているという印象でした。
発達相談を受けた頃までの長男(2歳10か月)の様子
長男が2歳10ヶ月の頃に発達相談を受けたのですが、それまでの様子はこんなかんじでした。
赤ちゃんの頃
- おっぱい飲んでもすぐ寝ない
- 抱っこしてないと1日中ぐずぐずしている
- 夜まとまって寝ない(2~3時間の細切れ。0歳で夜通し寝たことは記憶にない)
- 夜泣きする
- 人混みが嫌い
- 電車に乗るとぐずる
- ベビーカーが動いている時はいいけど、止まったり、お店に入るとぐずる
- 人見知り・後追いがあまりなかった
- 一人遊びが好き
- 身体の発達は割と平均的
- 目は普通に合う
- こちらが言っていることの理解もある
1歳~2歳
- 偏食が増えてきた(野菜のおかずはほとんど食べない。ポテト・唐揚げなどの揚げ物大好き)
- 数字・文字に興味を示す
- おもちゃを並べて遊ぶ
- ぐるぐる回って遊ぶ
- 手をつなぐのを嫌がる
- 上着や靴下を嫌がる
- 逆さバイバイ
- 動物に興味ナシ
- 地団駄踏んで癇癪を起す
- 自分で自分のことをやる気がない(食事・着替えなど)
- 決まったルートを通りたがる
- 公園は遊具広場スルーでひたすらお散歩
- 同じぐらいの歳の子が集まる場所が苦手(支援センター、子連れイベント、幼稚園の遊ぼう会のようなもの)
- 単語はそれなりに出ているが、質問に答えたりが出来ない
- 「ママ~」という呼びかけをしてこない
- しゃべっている言葉がほとんどエコラリア(遅延・即時両方)
- 外でもよく何かしゃべったり、歌ったりしてしまう(病院の待合室やバスの中など静かにしなくてはいけない場でも)
2歳半頃の長男。


とにかくこういった文字ブロックを並べるのが好きでした。

ブロック以外にも、こういったカップやトミカ、おままごとの野菜やフルーツを並べたりもしていました。
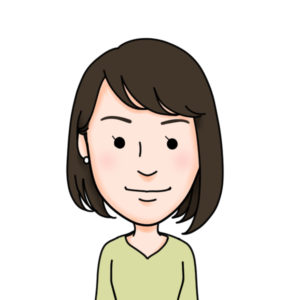
ザッと思いつくのでこんなかんじです。
赤ちゃんの頃は、すぐグズるので多少育てにくさはあったのかもしれませんが、第一子だったということもあり「こんなもんかなぁ・・・?」で過ごせました。
また、後追い・人見知りがなく、じじばばに預けられても大丈夫だし、ずっと一人遊びしてくれてたので、そういった部分はラクでした。
ただ、歩くようになり、自我が出てくると、癇癪が目立つようになりました。
全体的に、こだわりが強く・しつこい(笑)
ルーティーン・一人の世界・マイルールが落ち着く。といった感じでした。
言葉も単語は出ていたり、テレビのセリフや歌を覚えたりというのはよくできたのですが、こちらが「○○なの?」という質問をしても、それに返す。ということが出来ませんでした。
『言葉が出ない』というよりは、『会話が成り立たない』という表現が当てはまりますね。
発達相談の内容
そして、相談日当日。
市の保健センターで実施されたので、なんとなく病院のような雰囲気を感じたのか、部屋に入る前からギャン泣き。
部屋には、
- 小児科医(女医)
- 保健師
- 保育士2人
の方々がいて、本来なら、
子どもはおもちゃが広げられているスペースで保育士の方と遊びならが、その様子を見つつ、母親と小児科医・理学療法士の3人で面談
というかたちなのですが、長男がギャン泣きだったため、私が抱っこしながらの面談になりました。
面談では、相談に来るまでの子どもの様子を話す。というのが主です。
あとは、1歳半健診のように、絵が描かれたボードを指さして「これはなに~?」とか「わんわんどれ?」というのや、積み木を積んだりです。
簡単なテストはしますが、上記で書いたように、発達相談では発達検査はしません。
相談の内容を元に、今後療育へ通うかどうか。どういった支援をしていくか。というのを決定するかたちでした。
相談当日の長男の様子や、私が話した普段の様子から、小児科医の先生からは
[chat face="woman3" name="小児科医" align="left" border="red" bg="red"]“自閉症傾向”はあるけど、目も合うし、全く他人に関心がない。というようには感じられないから、親子教室へ通いながら様子を見ましょう。[/st-kaiwa1]
と言われたので、その翌月から週1回の発達支援教室に通うことになりました。
まとめ
以上、『発達相談』では何をするのか?というお話でした。
自治体によっても対応に差があるかとは思いますが、うちの自治体では、“診断”に関してはかなり慎重になっているという印象で、2~3歳で発達相談へ行ったからといって、すぐ診断というかんじではありませんでした。
発達障害の場合、特性が表れてきて、周りの子との違いが気になってくるのが2~3歳ということが多いような気がします。
その頃は、定型発達の子であっても『イヤイヤ期』で難しいお年頃。
「これは、発達が遅いのか・・・?ただの酷いイヤイヤ期なのか・・・??」
と、母親でも迷うところかと思います。
今は何でもネットで検索出来てしまう時代ですが、間違った情報や自分の子にぴったり当てはまる情報ではないことも多いです。
もし、子どもの育てにくさを感じていて、心の中にもやもやを抱えていたら・・・
早期に発達相談を受けたからといって、発達障害確定にはならないので、安心して、一度お住まいの自治体の児童発達支援担当の課に相談をしてみるといいと思います!
幼稚園入園前、外や遊び場で癇癪を起されるのがイヤで、引きこもりがちになっていってしまったのですが、発達相談へ行き、発達支援教室へ通うことで、私の気持ちもラクになったので、少し勇気を出して行ってみてよかったと思っています。
次は、『発達支援教室』ではどんなことをやっていたのか。というのを書ければいいなと思います。
▼おすすめ本▼
https://www.myradiantdays.com/entry/hattatsu-oyakokyoshitsu
https://www.myradiantdays.com/entry/tyonan-nensyo
[box06 title="あわせて読みたい"]
発達遅め長男(3歳0ヶ月)やっと、スプーン・フォークをまともに使えるようになりました!!その経緯をまとめ。
【発達障害グレーゾーン】4歳長男のトイレトレーニングが劇的に進んだきっかけ
[/box06]